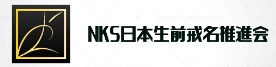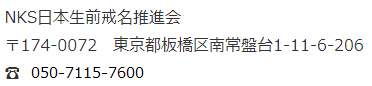
戒名とは
お釈迦様の時代
戒名かいみょう とは、出家でも在家でも、人が人生の途上で、
仏弟子になって仏道修行をしようと決めた時に、
師僧から戒を受けて仏教名を授かるその仏教名です。
いわばBuddhist Name なわけです。
2600年前の古代インドで、ネパールの小国の皇子であったゴータマシッダールタ(のちのお釈迦様、釈尊しゃくそん)が、人生の無常を感じ、国一番の美女の妻と生まれたばかりの可愛い息子とさらに王位を捨てます。
家を出る、世間を捨てることを、出家と言います。
しかし、この時代はまだ法名とか戒名というのはありませんでした。
男性の出家の比丘(びく)、女性の出家の比丘尼は、釈尊の僧団に加入するときに、修行の規範となる戒律を受けますが、戒名はありませんでした。
お釈迦様自身も、ゴータマという俗名で呼ばれていました。
弟子たちからは、ブッダつまり目覚めた人、”覚者”という尊称で呼ばれることもありましたが、仏教以外の人からはゴータマと呼ばれていたのです。
お釈迦様が入滅して、仏教が中国に伝播して以降、俗名を捨てて、僧名・法名つまり戒名を使うという風習が生まれました。東南アジアの諸国でも、インドでも、現在は、僧名、戒名を使用しています。
在家(ざいけ)の人、つまり世間にありながら、仏道を修めようとして、
正式に仏弟子とスタートするときも、戒名や法名をさずかります。
出家であろうが、在家であろうが、
仏弟子として修行するときには、三学を修めます。
戒・定・慧(かい・じょう・え)が修行の基本です。
戒とは戒律です。仏教を修行するのに、
仏弟子として心と言葉と行動(身口意しんくい)の規範が定められています。
仏の弟子としてスタートするときに、戒律を師から授かるのです。
逆に言いますと、戒律を授からずに出家はありえません。三学の基本だからです。
具足戒といって、比丘(男僧)にも比丘尼(尼僧)にも沢山の戒律があり、
それを守らねばなりませんでした。
出家の仏弟子がたくさん誕生すると、お釈迦様の時代にも、在家のままで修行したいという人も多く現れました。仏法を悟りたいけれど、家族を捨てるわけにはいかないので、今の生活のままで修行をするという人を在家と言います。
在家の男性は優婆塞(うばそく)と呼ばれ、女性の在家信者・修行者は優婆夷(うばい)と呼ばれます。
そういう人は、お釈迦様やそのお弟子から戒律を受けて在家として修行をしました。
在家の人が授かる戒は五戒あるいは十戒あります。
仏弟子としての自分の戒を自己に誓います。
戒名・法名・法号の由来-中国から日本へ
勿論、中国に仏教がとどまっていた時代には、出家であろうが、
在家であろうが、戒名を頂戴するのに金銭的な授受はなかったのです。
現在の戒名は、仏教が日本に伝来してから、聖武天皇が初めて戒名を頂戴したと言われています。
また死者を弔うのは、もともと仏教僧の仕事ではありませんでした。
仏典によれば 大涅槃(死期)が近づいた釈尊に弟子の1人がお釈迦様の葬式の仕方について尋ねると、弟子達にこう言われました。
「あなた方出家者は私の葬儀、遺骨の供養礼拝にかかわってはならず、修行に専念せよ。遺骨の供養は在家 ( 非出家者 ) の信者達がするであろうから。』
釈尊の行動を記した原始仏教経典を読むと、釈尊や弟子たちが墓場で坐禅をしている記事が多々あります。
まだお寺もなかったです*1から、人気のない、森林か墓場で坐禅修行されていたのです。
死者を葬るのは出家の仕事ではなかったのです。
つまり葬儀法事は僧侶の仕事ではないのです。
特に、先祖を祭る先祖崇拝というのは、迷信の多いバラモン教にあっても、知的な仏教にはありません。
葬祭を司るのはバラモン階級の仕事でした。
先祖崇拝は、仏教が中国や一部韓国を経由して日本に伝わったときに、儒教思想が混じってしまったことによります。
インドでは僧侶は死者を弔う仕事はしませんが、
死者を弔う職業の人がいない日本では、僧侶がそれをするようになりました。
そして上で述べたように、本来、戒名は、生きているときに仏弟子となって戴くものです。
ところが、江戸時代に、死後に、戒名をつけるようになりました。
これは、生きている間に仏教徒でなかったので、死後に仏教徒つまり出家にして間に合わせようという発想なのです。
これを没後作僧(ぼつごさそう)と言います。つまり亡くなってから僧にするということです。
江戸時代には寺院がある意味役所のような働きをしていました。
人の戸籍は寺院が管理していたのです。
その時、キリスト教を排する意味もあって強制的に檀家制度が確立されました。
いわゆる寺請制度です。
寺院収入を安定させるためにも、死者に対して葬儀にともない高額な戒名料を取るようになりました。
当時文字を読める人々というのは僧侶などに限られていて、従って僧侶は支配階級であったわけです。
ですから、文字の読める僧侶がそうでない一般人の人心を操ることは容易だったのです。
現代に至っても、いまだに江戸時代の封建体制の名残りで、死後に戒名をつけていますし、葬祭については僧侶の仕事となっています。
そして現代の日本にあっては、物価の高騰と共に戒名の相場は、値上がり(?)を続けています。
今や戒名の値段は高額も高額、一文字10万円とも言われ、数十万円が相場だとも言われています。
これでは、いわゆる坊主丸儲けと疑われてもしようがありません。
親族がなくなってあたふたとしている時に余裕などありません。その時に請求されてしまうと、納得できないながらも支払ってしまいます。
残念ながら、葬式仏教にひたっている大多数の僧侶自身が、釈尊の正しいメッセージを伝えてきていないので、一般人は何が仏教の教えで、何がそうでないか、どれが真実でどれが迷信や慣習に過ぎないことなのかもわかりません。
まして、見えない死後のことです。
平生から、正しい仏教の史実を知り、戒名の知識があれば、悪しき慣習にも、きっぱりと理性的に対処することができるようになります。
すでに述べましたように、戒名は元来、仏弟子となったときに、受戒している僧侶から(だから僧侶はすでに戒名を持っています)戒を授かりますが、その時に名前をいただくことです。
戒名は人生の途上にいただくものであって、死後につけるのは遅いわけです。
つまり、仏教は生きている人のためであって死者のためではありません。
生前でも、仏教を信仰していない人なら、戒名を得なくてもいいわけです。
まして死後に戒名をつけてもらう必要はありません。
無戒名つまり戒名をつけないで俗名のままでよいわけです。
無戒名だからといって死後の運命が良くないとか、残されたものに良くないことがあるというようなことは決してないのです。
かといって、世間の風習に反対して行動するのは心配だという方も多いでしょう。
5万円がお得になるお仏壇・お位牌の購入方法
当NKS日本生前戒名推進会をご利用いただきましたお客様には
他所では教えてくれないお位牌とお仏壇を安く購入する方法をお教えいたします。
数万円がお得になりますので、この無料レポートをぜひお読み下さい。
売り込みはありませんのでご安心ください。
無料レポート【お位牌とお仏壇を安く購入する方法】の申込み
戒名授与されたお客様限定の特別情報となります
故人の戒名、生前戒名を授与していますーNKS日本生前戒名推進会
信士・信女、釋・釋尼(しゃくに)の通常戒名は19,000円 (桐箱なしなら18,000円+送料全国500円)、居士・大姉3万円、禅定門・禅定尼3万円
院号付き戒名は、6万円(7文字以下の院号戒名)または7万円(8文字以上の院号戒名)にて授与しています
ただし、院号大居士、院号清大姉は8万円となります 院号なしの大居士・清居士・清大姉・清信士・清信女オプション(+10,000円)
院殿号戒名料金は27万円にて授与
子供さんの場合:水子1万円、15才以下(嬰児・嬰女、孩子・孩女、童子・童女) 15,000円
※ 戒名は宗派担当僧侶が授与いたしますが、葬儀や法事の僧侶派遣はしておりません
※ お位牌は仏具店・仏壇店またはネット通販でお客様直接ご購入下さい 当会から発行する用紙を持ってご依頼下さい